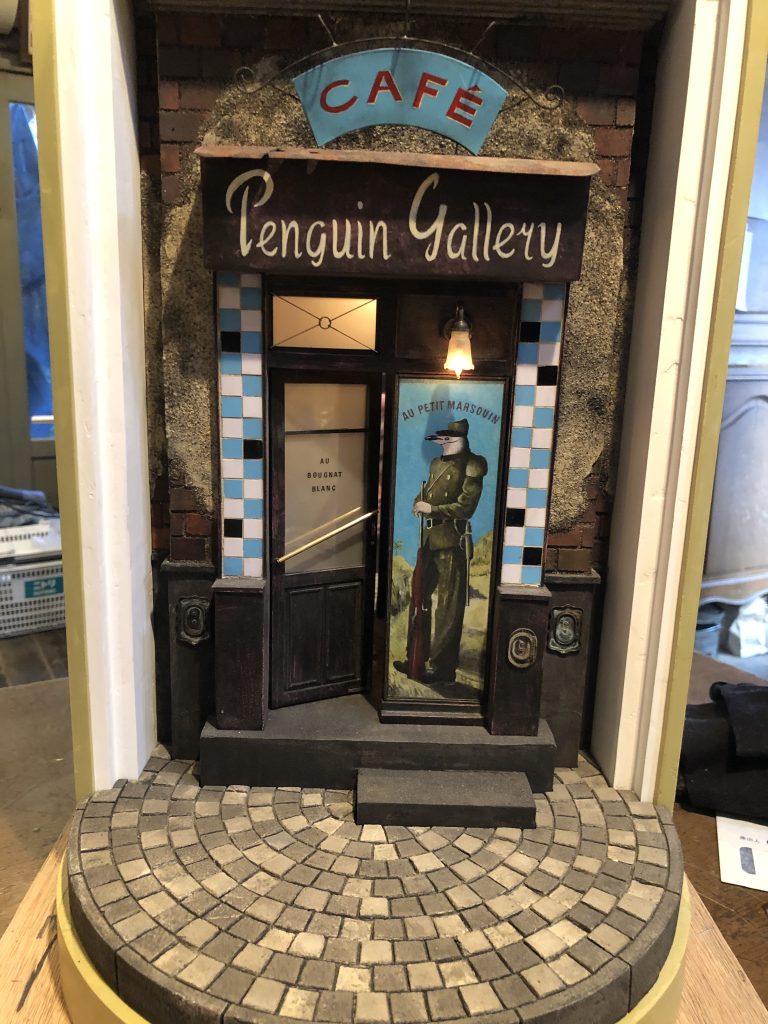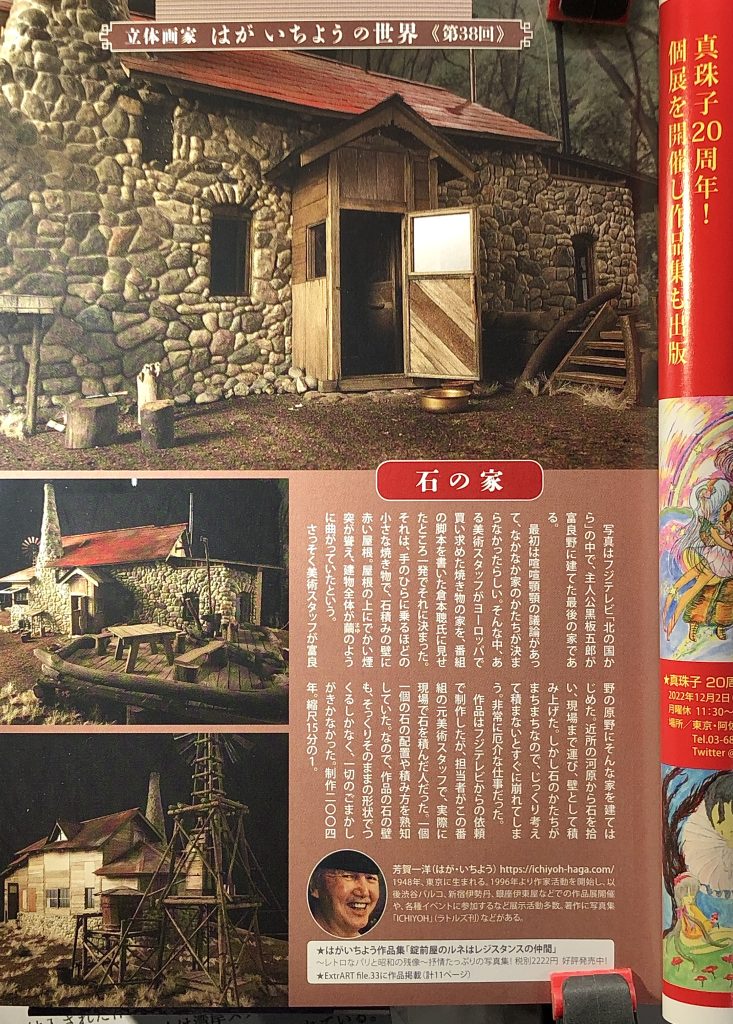新ブーランジェリー制作教室の初回講座が、予定通り、11月27日の午後、小生のオンボロスタジオで開催された。
前回述べたように抽選で選ばれた8名がひとりも欠けることなく全員集合。はるか松山からジェット機で通う生徒もいらっしゃり、なかなかの盛りあがりだった。ただ全員新人なので人数の割にシーンと静まり返っていて、誰も無駄口をたたかない。常にだれかが余計なおしゃべりをしているような、ゆる〜いクラスになれきっている自分にとっては、そこがちょっと落ち着かず、時間がやたらと長く感じた。
ドールハウスギャラリー・ミシールの副代表を務めるタカハシさんや、スズキさん(両者男性)など、見るからに酒好きそうな参加者もいらっしゃり、放課後活動(居酒屋へ行くこと)への仄かな期待を寄せているフシもあったが、この日は例のW杯コスタリカ戦があった日だ。調べると、キックオフが午後7時半とのこと。それじゃあ放課後活動は今回はあきらめましょう‥ということになり、講座終了後は、みんな速攻で家へ帰った。
このクラス、次回は1月8日の午後開催されます。