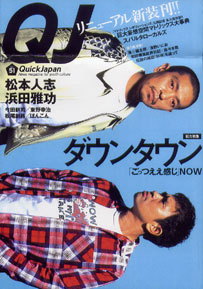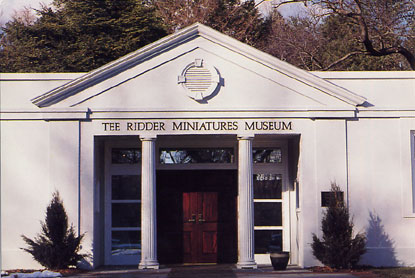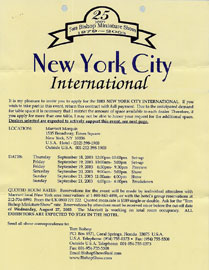前々回のトークスでは銀座・伊東屋に拙作の小さな展示コーナーが新設されたことをお知らせしたが(2003年11月4日付け)今回もまた伊東屋に関しての話題である。
伊東屋とは、言わずと知れた日本一有名な文房具店のことである。創業は明治37年(1904年)6月16日とのことなので、来年(2004年)の6月で、ちょうど創業100年を迎えることになるそうだ。長い歴史である。その100年のあいだ、店を閉鎖していた戦乱のいっときを除き、ずっと「日本の文具店・ナンバーワン」の地位をキープし続けたというのだから、モノスゴイものだと、改めて感じる。したがって来年の6月には、大々的な慶賀の式典が予定されているとのことだが、式には創業当時の店舗を現した模型展示物が一個必要とのことで、少し前から、ぽちぽちと作り始めたところだ。とてつもなく栄誉ある仕事を与えられたものだと、身の引き締まる思いで、慎重の上にも慎重な態度で、制作を開始したところである。
下に写真を掲載したが、これが創業当時の店舗である。資料はこの写真一枚きりで、今回の私の任務は、下の写真を、雰囲気のある重厚な立体造形物に作り直すという、とても難しそうな仕事である。写真を見ると、複雑な形状の造形看板がすぐに目につき、2階のベランダには独特の模様を組み込んだスチール製の手すりがついているなど、そのどれもが造る者をおびえさせるに十分である。と同時に、大いなる意欲をわかせるにも十分な面構えであるとも言える。
この美しい店舗を造ったのは伊藤勝太郎(いとう・しょうたろう)という方で、彼は明治8年に、銀座7丁目でお生まれになっている。両親は洋品店(洋服屋)を営んでいたそうだが、文明開化のころの洋服は、正に最先端グッズだったはずである。勝太郎氏は長男だったので、成長すると親の商売を継いで商人となったが、やがて彼は、今度は「洋品小間物」を専門に取り扱う店を、帝国博品館の中に開いた。帝国博品館とは、いまでも銀座7丁目に現存する博品館(現オモチャ屋)の前身だが、当時は2階建ての長屋のような構造をした、今で言うテナントビルのようなものだったらしい。勝太郎氏はその一区画に新しい店を構えたのだが、たまたま隣りが文具店だった。そして、ほどなく文具店は経営危機におちいり、「居ぬきで店舗ごと、買い取ってくれないか‥」とのはなしが、勝太郎の元に舞い込んだ。
伊東屋100年の、幕開けストーリーである。
伊藤勝太郎30歳のときのことだった。
「居ぬきで、ぜんぶ買ってくれ」と言われた勝太郎だが、写真をじっくり眺めればわかるように、どこもかしこも、ぜんぶを作り変えてしまっただろうことが、一目瞭然である。STATIONERY(ステーショナリー)と英文が入った美術的なサインボードや、その上に乗っかったゴシック風・造形看板など、どれもが芸術的で、しかも飛び切りモダンだ。そうとうな気合を入れて造り、また莫大なカネを掛けただろうことが見て取れる。新しい商売に賭けた伊藤氏の気概が伝わってくるようだ。
そういう訳で、伊東屋の一号店は、現在の場所にあったわけではなく、現・博品館の位置にあったのだ。そして、開店からわずか6年後の明治42年に、今度は銀座3丁目(現・伊東屋のすぐ近所)に引っ越すと同時に、ここに新築3階建てのビル型店舗を建ててしまったのだから、青年社長・伊藤勝太郎氏が、大変な商才の持ち主だったことを認めないわけにはいかない。また当人の姓は伊藤なのに、敢えて「伊東屋」という屋号を掲げるあたりにも、独特の感性を感じる。(もし筆や和紙など、もっぱら和物を中心に取り扱うのなら「伊藤屋」でよいが、西洋の文具にはやっぱり「伊東屋」のほうが似合うような気がする。また、そういうことを考えるというヒラメキに、抜群の才能を感じる。)
―以上は「ITO-YA」のウェブサイト http://www.ito-ya.co.jp/ より「伊東屋物語」を読んで、少し勉強しました。
そして現在、創業者・伊藤勝太郎氏から数えて4代目にあたる方が、現社長・伊藤髙之(いとう・たかゆき)氏である。いかにも老舗の社長といった高貴な風格を漂わせた、ダンディーな紳士であると同時に芸術や音楽にも造詣が深く、若い頃にはチェロを演奏していたとお伺いした。その伊藤4代目社長からのご指名にあずかり、このたびこのような重大な任務を任せられたというわけで、とてもおちおちしてはおれない。実は数ヶ月前より、2階の手すりや造形看板など、特にむずかしそうなパーツについての研究は開始していて、あるものは専門の業者にパーツを依頼したり、またあるものはアメリカから取り寄せたりしながらも、徐々に主要な部品がそろいつつあり、それらをまとめて作品にするという仕事を、恐る恐る、つい最近開始したところである。
完成は2004年、5月の予定。
乞うご期待!

写真提供・株式会社伊東屋
2003年12月16日