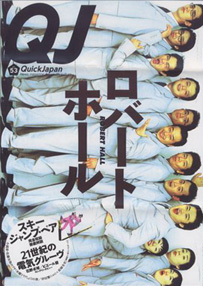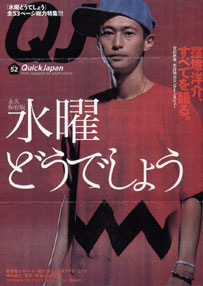クリスマスにテキサスの農場が爆破されることもなかったし、元旦にミサイルが皇居に突っ込むこともなく、意外とおだやかな正月だった。てっきり大事件が勃発するとばかり思っていたが、アルカイダの諸君は一体どうしちゃったのだ。ま、それはともかく、ずっと昔から私はこの時期、特に変わった行動はせず、いたって普段どおりに過ごしている。
「2003年12月31日」
「2004年1月1日」
「2004年1月2日」
「2004年1月3日」
そしてきょう1月4日は、先ほど、朝の5時半から、ずっとパソコンの前に座っている。私のはノート型パソコンだが、それが作業用テーブルのすぐ横に置いてある。本当は一刻も早く伊東屋の続きを始めたいのだが、次は、どうしても丸ノコによる切断が必要で、いま待機しているところなのだ。丸ノコは騒音が伴うので、あんまり早朝だと使えないからである。仕方がないので、いまこのトークスを書いている‥。
以上までの記述を見ると、たいへん早起きのようにも見えるが、これは、たまたまである。あるとき一回でも早朝まで仕事を続けたりすると、翌日起きるのが遅くなり、その日を境にして一転夜型に転じることもある。要は体力の続く限り仕事をし、眠くなったら寝るというのが就労パターンで、起きる時間は特に定まっていない。そして正月といえども、通常どおりの仕事をこなしていることがおわかりいただけたと思う。私には趣味というものがなく、普段本は読まないし、スポーツをやるという習慣もない。家族でどこかに出掛けることもないので、仕事以外のことは常に一切やらぬのだ。これはずっとそうで、以前商売をやっていたときにも365日、一日たりとも休んだことがなかった。日・祭日も営業したし、12月も、31日まで営業し、そして正月の2日が、たいがい初売りだった。福袋が良く売れた。元旦はそのための準備だから、もちろん休まない。大体からしてその頃は、店を閉めるのが午後の7時や9時といったありさまで、私は9時より早く帰宅することがなかった。だから家族そろっての食卓もなく、そんなことが約20年間続いた。考えれば私のオヤジも商売をやっていたので、元旦の朝以外には家族と一緒の食卓についたことがなかった。その元旦も、夕方にはひとりでどこかへ出掛けていたので、私の父が家族と供に、家で夕飯を取ったことは多分一回もなかったはずである。お陰で代々芳賀家には、家族そろっての食卓や、一家でどこかへ出掛けるといった伝統(習慣)がなく、正月も右へ習え、なのだ。
2004年元日の集合写真