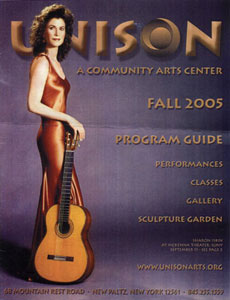写真が苦手(撮るのがヘタ)ということは、以前にもこのトークスで書いたことがあった。だから先日ニューヨークへでかけたときも、カメラは持っていかなかった。(というより、僕は一台もカメラを持っていないのだ。)だから同行のスギちゃん(杉山武司氏)に、撮影はみんなまかせた。このときに撮った写真100枚以上を、先日CDに焼いて持ってきてくれた。中にはボツにするのがもったいないような名ショットもあったので、その中の一枚をここに掲載することにする。
下の写真はユニソンでのオープニングレセプションに駆けつけるため、一回マンハッタンに入らねばならず、当日の昼ごろ、ブルックリンブリッジをわたっているときのものだ。
いい~写真だねえ~、ほんとうに。
ほんの少し斜めになっているアングルがいい。
そしてどんよりとした曇り空がこの橋にぴったりで、鉄の持つ重苦しいムードをいっそう際立たせ、そこがこの写真のいいところ。リベットがビシッーっと並んだこのいかつさ、ゴツさ、このレトロさは、正に鉄の芸術品と呼ばれるにふさわしく、開通したのは1883年のことだというから、日本でいえば明治初期のこと。大好きな橋なので、いつかわたりたいと願っていたが、今回はじめて実現した。このすぐ上流にはマンハッタンブリッジというのがあって、こっちは高速ハイウェイに直結しているため、ニューヨーカーたちはそっちを使うことのほうが多いと聞いた。だからこんにち、ブルックリンブリッジをわたるのは、どちらかというと近郊の方々(主にブルックリン在住の方々)にかぎられているのかもしれない(あんまりよく知らないが‥)。
金属工作とリベット打ちの名手である佐野匡司郎氏あたりがおつくりになるのにちょうどよい雰囲気をもっているのではなかろうか‥。
―――前回につづき今回も橋の話題となりましたが、ニューヨーク行きに関しては、前回と前々回のトークスにも記載があります。

2005年10月22日